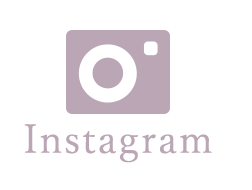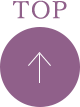内科
当院の内科について
総合内科専門医の院長による診察・検査
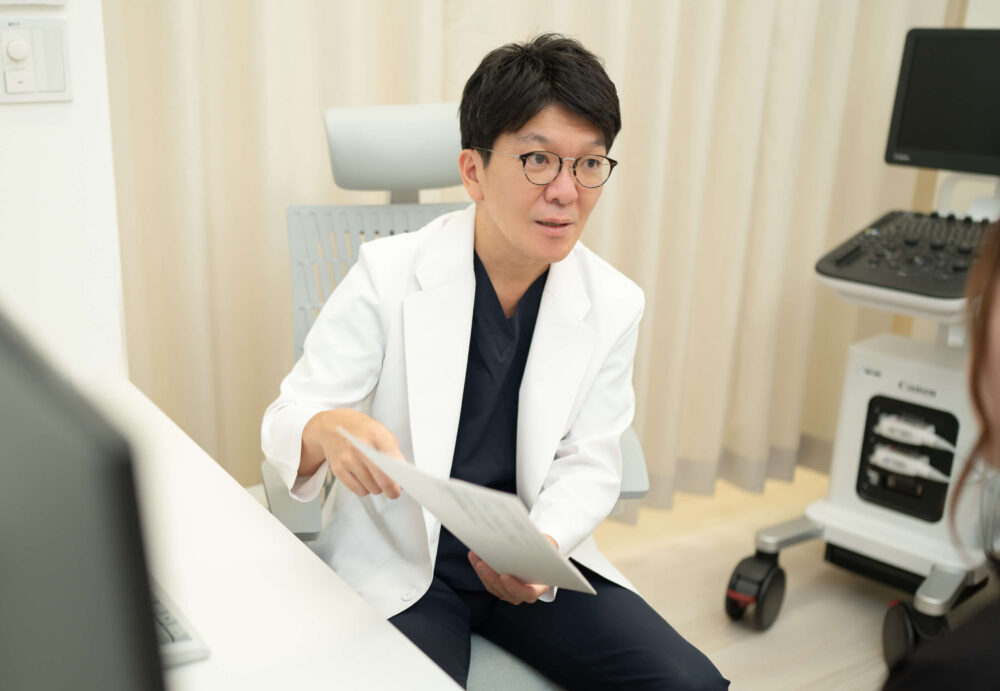 日本内科学会・総合内科専門医である院長が、内科にかかわる疾患・症状を幅広く診療します。頭痛、発熱、のどの痛み・咳、鼻水・鼻づまり、動悸・息切れ、めまい、むくみ、不眠などの気になる症状がございましたら、お気軽にご相談ください。
日本内科学会・総合内科専門医である院長が、内科にかかわる疾患・症状を幅広く診療します。頭痛、発熱、のどの痛み・咳、鼻水・鼻づまり、動悸・息切れ、めまい、むくみ、不眠などの気になる症状がございましたら、お気軽にご相談ください。
健康診断で引っかかったという方も、お早目にご相談ください。
こんな症状は内科まで
お越しください
以下のような症状のある方、健康診断・人間ドックで異常を指摘された方は、お気軽に当院の内科にご相談ください。
- 頭痛
- 発熱
- 倦怠感
- のどの痛み・咳
- 鼻水・鼻づまり
- 吐き気・嘔吐
- 腹痛・便秘・下痢
- 食欲不振・体重減少
- 動悸・息切れ
- めまい・ふらつき
- 貧血
- むくみ
- ほてり・のぼせ
- 不眠
- 耳鳴り
内科で診療する疾患
内科では、主に以下のような疾患を診断・治療します。
- 風邪・インフルエンザ
- 新型コロナウイルス感染症
- 気管支炎
- 肺炎
- 喘息
- 糖尿病
- 高血圧症
- 脂質異常症
- メタボリックシンドローム
- 高尿酸血症・痛風
- アレルギー性鼻炎(季節性・通年性)
- 甲状腺機能亢進症(バセドウ病)
- 甲状腺機能低下症(橋本病)
- 蕁麻疹
- 帯状疱疹
- 膀胱炎
- 腎盂腎炎
など
当院で対応する検査
血液検査
レントゲン検査
心電図検査
超音波検査
尿検査
糖尿病内科
当院の糖尿病内科について
糖尿病をはじめとする生活習慣病のサポート
 糖尿病は、発症した年齢やライフスタイル、合併症の有無などによってその治療が千差万別です。
糖尿病は、発症した年齢やライフスタイル、合併症の有無などによってその治療が千差万別です。
日本糖尿病協会・糖尿病認定医である院長が、薬物療法だけに頼るのではなく、食事・運動習慣を含めた生活習慣の改善についても、個々に合った細やかな指導やアドバイスを行います。
血糖値やHbA1cの数値が正常でなかった方、すでに何らかの症状が現れている・合併症をお持ちの方も、お早目にご相談ください。高血圧症や脂質異常症といった他の生活習慣病についても、専門性を活かした治療を行います。
こんな症状は糖尿病内科まで
お越しください
以下のような症状のある方は、お気軽に当院の糖尿病内科にご相談ください。
- 健康診断や人間ドックで異常を指摘された
- よく食べ過ぎたり飲み過ぎたりしてしまう
- 味の濃いもの、脂っこいものが好き
- 外食、コンビニ弁当、レトルト食品などで食事を済ませがち
- 清涼飲料水、甘いコーヒーなどを日常的に飲んでいる
- 運動をする習慣がない
- 20代の頃より10kg以上体重が増えた
- 忙しく休めていない、睡眠不足が続いている
- 仕事や家事、子育てなどで、慢性的にストレスを抱えている
- 喫煙をしている
生活習慣病
 生活習慣病とは、暴飲暴食・栄養の偏り、運動不足、ストレスなど、生活習慣の乱れを主な原因として発症する病気の総称です。糖尿病・高血圧症・脂質異常症・メタボリックシンドローム・高尿酸血症(痛風)などがこれに該当します。
生活習慣病とは、暴飲暴食・栄養の偏り、運動不足、ストレスなど、生活習慣の乱れを主な原因として発症する病気の総称です。糖尿病・高血圧症・脂質異常症・メタボリックシンドローム・高尿酸血症(痛風)などがこれに該当します。
生活習慣病の特徴として、初期の自覚症状の乏しさが挙げられます。そのため気づかないうちに進行し、時に命にかかわるような重大な合併症の引き金になってしまうということがあります。
特に以下に該当する方は、生活習慣病になっている可能性があるため、たとえ自覚症状がない・少なくても、お早目に当院にご相談ください。
総合内科専門医・糖尿病専門医である院長が、お一人おひとりに合った検査・治療を行います。
糖尿病
糖尿病は、インスリンが十分に働かない・分泌量が少なくなることで、血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)が高くなる病気です。高血糖状態が続くことで、全身の血管にダメージが蓄積し、動脈硬化を進行させます。そして動脈硬化は、心筋梗塞や脳卒中など、命にかかわる合併症のリスクを高めます。
糖尿病は初期症状に乏しい病気で、ある程度進行してから、のどの渇き・多飲・多尿、皮膚の乾燥、異常な空腹感、手足の感覚低下といった症状が現れます。
原因としては、食べ過ぎ・飲み過ぎ、運動不足、喫煙、ストレス、遺伝的要因などが挙げられます。
糖尿病の合併症
糖尿病網膜症
目の奥にある網膜が障害され、視野のかすみ、視力低下といった症状を引き起こします。長期にわたって放置していると、失明に至ります。
糖尿病腎症
腎臓の細い血管が障害されることで、腎機能が低下します。放置していると腎不全となり、人工透析が必要になります。
糖尿病神経障害
手足の感覚異常・しびれ・痛みといった症状が引き起こされます。小さな傷口からの感染から足壊疽を起こし、足の切断を余儀なくされるケースもあります。
高血圧
血圧が正常な範囲を超えて高い状態が続く病気です。心臓、血管に負担がかかることから、心筋梗塞などの心臓病、脳卒中、腎臓病などのリスクが高まります。
生活習慣病の中でも特に自覚症状が乏しく、多くは健康診断などで行う血圧測定をきっかけに偶然見つかります。原因としては、塩分の摂り過ぎ、肥満、お酒の飲み過ぎ、運動不足、喫煙、ストレス、遺伝的要因などが挙げられます。
脂質異常症
血液中の脂質のバランスが異常になる病気です。血液中のLDLコレステロールや中性脂肪が多すぎる、またはHDLコレステロールが少なすぎる場合に診断されます。
高血圧症と同様、ほとんど自覚症状がありません。原因としては、食べ過ぎや飲み過ぎ、食生活の欧米化、運動不足などが挙げられます。
高尿酸血症(痛風)
高尿酸血症とは、プリン体の分解時にできる「尿酸」の血中濃度が高くなる(7.0mg/dlを超える)病気です。高尿酸血症の段階では無症状ですが、放置していると尿酸が足の関節などで結晶化し、激しい痛みと腫れを招き、これを「痛風」と言います。痛風は発作的に繰り返され、次第に間隔が短く・症状が強くなります。
メタボリックシンドローム
男性であれば腹囲85cm以上、女性であれば腹囲90cm以上あり、なおかつ血圧・血糖・脂質のうち2つ以上が基準値から外れている状態を、メタボリックシンドロームと言います。高血圧症・糖尿病・脂質異常症のリスクが非常に高い状態であるため、早急に治療が必要です。
消化器内科
当院の消化器内科について
消化器病専門医による丁寧な説明と診察
 当院院長は、日本消化器病学会の消化器病専門医です。消化器領域の疾患・病態を深く理解し、高い専門性をもった医療を提供します。また、分かりやすい言葉を使い、丁寧に説明・診察をいたします。
当院院長は、日本消化器病学会の消化器病専門医です。消化器領域の疾患・病態を深く理解し、高い専門性をもった医療を提供します。また、分かりやすい言葉を使い、丁寧に説明・診察をいたします。
消化器内視鏡専門医の確かな技術で安心の胃・大腸カメラを実施
 胃カメラ検査・大腸カメラ検査は、日本消化器内視鏡学会・消化器内視鏡専門医である院長が担当します。安全性・確実性を高めた苦痛の少ない内視鏡検査により、患者様の健康と安心をお守りします。
胃カメラ検査・大腸カメラ検査は、日本消化器内視鏡学会・消化器内視鏡専門医である院長が担当します。安全性・確実性を高めた苦痛の少ない内視鏡検査により、患者様の健康と安心をお守りします。
- 初診当日の胃カメラが可能
- 土曜・日曜の検査が可能(日曜は月に1~2回実施)
- 午前・午後も検査を実施で予約が取りやすい
- 院内or自宅での下剤服用の選択が可能
- 鎮静剤の使用でリラックスした状態での検査が可能
- 胃カメラ・大腸カメラの同日検査が可能
- 人間ドックを実施
- リカバリースペースを完備
- 大阪市が認めた高水準消毒薬を使用した内視鏡自動洗浄機を導入
- 高性能な内視鏡検査システムを導入
こんな症状は消化器内科
までご相談ください
 消化器にかかわる以下のような症状がございましたら、お気軽に当院の消化器内科にご相談ください。
消化器にかかわる以下のような症状がございましたら、お気軽に当院の消化器内科にご相談ください。
- のどの痛み
- 飲み込みづらさ
- 胸やけ、胸の痛み
- 吐き気、嘔吐
- ゲップ、呑酸
- 胃やみぞおちの痛み
- 胃の重い感じ、胃もたれ
- 原因不明の背中の痛み
- 腹痛、腹部膨満感
- 下痢、便秘
- 血便、粘血便
- 残便感、便が出にくい
- 便が細くなった
- 全身倦怠感
- 食欲不振、体重減少
- 黄疸
食欲不振
食欲が低下して食べたい気持ちが起こらない状態です。
原因の例:胃炎・胃潰瘍・肝臓病・感染症・ストレスや精神的要因・薬の副作用など。
一時的なこともありますが、長く続く場合は内科的な病気が隠れている可能性があります。
体重減少
意識的なダイエットではなく、生活習慣の変化がないのに体重が減ることです。
原因の例:がんや甲状腺機能亢進症、糖尿病、慢性消化器疾患、抑うつなど。
短期間で大きく減少する場合は注意が必要です。
胸やけ
胸のあたりが焼けるように熱く、不快に感じる症状です。
原因の例:逆流性食道炎(胃酸の逆流)、胃炎、胃潰瘍など。
頻繁に起こると、食道粘膜の炎症やバレット食道などのリスクにつながることがあります。
のど・食道のつかえ感
食べ物や飲み物がのどや胸の途中で止まるように感じる症状です。
原因の例:逆流性食道炎、食道炎、食道がん、神経や筋肉の障害など。
持続する場合は精密検査が必要になります。
お腹の張り(腹部膨満感)
お腹がガスで張ったり、重たい感じがする状態です。
原因の例:便秘、過敏性腸症候群、消化不良、肝疾患や腹水、腫瘍など。
軽度で一時的なこともありますが、繰り返す場合は要注意です。
便通異常(便秘・下痢)
便が出にくくなったり(水分が少ない硬い便)、逆に柔らかすぎて頻繁に出ることです。
原因の例:食生活の乱れ、過敏性腸症候群、感染性腸炎、大腸ポリープや大腸がんなど。
急に便通が変化したり、血便を伴う場合は早めの受診が必要です。
黄疸
皮膚や白目が黄色く見える症状です。
原因の例:肝炎、肝硬変、胆石、胆道閉塞、膵がんなど。
ビリルビンという色素が血液中に増えることで起こります。全身のだるさやかゆみを伴うこともあり、重い病気のサインであることが多いです。
消化器内科で診療する疾患
胃の病気
急性胃炎
慢性胃炎・萎縮性胃炎
びらん性胃炎
胃・十二指腸潰瘍
胃ポリープ
胃がん
ピロリ菌感染症
機能性ディスペプシア
胃アニサキス症
胃腺腫
胃粘膜下腫瘍 など
大腸の病気
急性腸炎
大腸ポリープ
大腸がん
潰瘍性大腸炎
クローン病
過敏性腸症候群
虚血性大腸炎
大腸憩室炎
腸閉塞 など
食道の病気
逆流性食道炎
食道がん
バレット食道
食道裂孔ヘルニア
食道静脈瘤
食道アカラシア など
肝臓・胆道、膵臓の病気
脂肪肝
肝炎
胆石
胆嚢ポリープ
膵がん
膵炎 など
胃炎
胃の粘膜に炎症が生じた状態で、急性と慢性があります。原因はピロリ菌感染、薬(NSAIDs)、ストレス、飲酒などが挙げられます。症状は胃の痛み、吐き気、食欲不振などで、原因に応じた治療(ピロリ菌除菌や薬物療法)を行います。
胃潰瘍
胃の粘膜がただれ、深く傷ついた状態です。ピロリ菌感染や薬の副作用(鎮痛薬など)が主な原因です。みぞおちの痛み、吐血や下血が症状として現れます。治療は胃酸を抑える薬やピロリ菌除菌を中心に行います。
食道がん
食道の粘膜に発生する悪性腫瘍です。喫煙・飲酒・熱い飲食物の習慣などがリスク要因となります。初期は症状が出にくいですが、進行すると食べ物のつかえ感・胸の痛み・体重減少などがみられます。治療は内視鏡治療、手術、放射線や化学療法などを行います。
逆流性食道炎
胃酸が食道に逆流することで、食道の粘膜に炎症が起こる病気です。主な症状は胸やけ、酸っぱい液が上がる、咳やのどの違和感などがあります。生活習慣の改善や、胃酸を抑える薬(PPIなど)で治療を行います。
感染性腸炎
細菌やウイルスによって腸に炎症が起こる病気です。発熱、腹痛、下痢、血便などの症状を伴います。多くは自然に回復しますが、重症例では点滴や抗菌薬が必要となります。
炎症性腸疾患(IBD)
代表的なものは潰瘍性大腸炎・クローン病です。自己免疫反応が関与すると考えられており、慢性的な腹痛や下痢、血便が特徴です。再燃と寛解を繰り返すため、継続的な治療と管理が必要です。
脂肪肝
肝臓に中性脂肪が過剰にたまった状態のことを指します。飲酒が原因の「アルコール性」と、肥満や糖尿病が関係する「非アルコール性(NAFLD)」があります。多くは症状がなく、放置すると肝炎や肝硬変に進行することがあります。食事・運動習慣の改善が基本となります。
肝炎
ウイルス感染(A型・B型・C型など)、アルコール、自己免疫などが原因で肝臓に炎症が起こる病気です。だるさ、食欲不振、黄疸などがみられることがあります。原因に応じて抗ウイルス薬や生活習慣改善での治療を行います。
胆石
胆のうや胆管に「石(結石)」ができる病気です。症状がないこともありますが、右上腹部の激しい痛み(疝痛発作)、吐き気、発熱を伴うこともあります。治療は症状の有無や大きさに応じて、経過観察や手術(胆のう摘出)を検討します。
胆嚢ポリープ
胆のうの粘膜にできる隆起の事を指します。多くは良性で自覚症状もありませんが、大きさや形によっては胆のうがんとの区別が必要になります。定期的な超音波検査で経過を確認する事が多いです。
膵がん
膵臓にできる悪性腫瘍で、進行が早く予後が厳しいがんの一つです。初期は症状が乏しいですが、進行すると黄疸、体重減少、背中の痛みなどが現れます。外科手術、抗がん剤、放射線療法を行います。
膵炎
膵臓に急性または慢性の炎症が起こる病気です。原因は胆石、アルコール、多量の食事や脂質摂取などが挙げられます。急性膵炎は激しい上腹部痛、吐き気、発熱を伴い、入院治療が必要になることもあります。慢性膵炎では消化不良や糖尿病を引き起こすことがあります。
当院で対応する検査
血液検査
レントゲン検査
心電図検査
超音波検査
尿検査
内視鏡検査(胃カメラ・大腸カメラ)