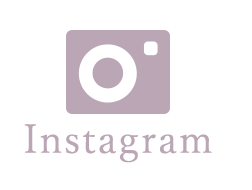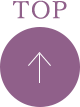以下に該当する便秘症状は
危険かも!
便秘は比較的身近な症状です。水分や食物繊維が不足しただけでも、便秘になります。また無理なダイエットや加齢に伴う腹筋力の低下なども、便秘のリスクを高めます。こういった便秘では、水分・食物繊維をしっかり摂ったり、食事と運動を組み合わせた正しいダイエットに切り替えたり、筋力をアップさせることで改善が可能です。
一方で、以下のような便秘は危険度が高くなります。放置せず、すぐにご相談ください。

- これまで快便だったのに、急に便が出なくなった
- 便秘と下痢を交互に繰り返している
- 便が細くなった
- 強い腹痛を伴う便秘
- 便秘に加え、吐き気や嘔吐、発熱が続いている
- 血便が出た、便潜血検査で陽性だった
こんな症状の方も
お早めにご相談ください
上記の便秘ほど危険度は高くないものの、以下のような便秘にお悩みの方も、お早目に当院にご相談ください。何らかの病気が原因になっている可能性もあります。
- 排便時に痛みがある
- 排便のために下剤を使うのが当たり前になっている
- 排便後もお腹がすっきりしない(残便感)
- コロコロとした便が出る
便秘になる原因と種類
便秘は大きく、機能性便秘と器質性便秘に分けられ、それぞれ原因が異なります。
機能性便秘
便秘の大半は、機能性便秘が締めています。
機能性便秘とは、自律神経のバランスの乱れなどを原因として、大腸が機能不全に陥ることで発症する便秘です。
弛緩性便秘
腸管が弛緩し、蠕動運動が不十分になるために、便が大腸で長く留まるタイプです。長く留まる分、水分の吸収が進み、便が硬くなって肛門から出にくくなります。
女性、ご高齢の方に多い便秘です。
主な原因としては、水分や食物繊維の不足、運動不足、加齢に伴う腹筋力の低下、無理なダイエットなどが挙げられます。
けいれん性便秘
副交感神経が過度に興奮し、腸管が過度に緊張して便の運搬がうまくいかなくなるタイプです。コロコロとした便が出ることが多くなります。
主な原因としては、環境の変化等のストレス、過敏性腸症候群などが挙げられます。
直腸性便秘
便が直腸に達しているのに、センサーが反応せずに排便がなされないタイプです。多くの場合、下腹部の張りを伴います。
主に、トイレを我慢する習慣が原因となり、センサーが鈍ります。寝たきりなどで排便に介助が必要な方、痔で排便が辛い方にもよく見られます。
器質性便秘
大腸がん、腸閉塞、腸管癒着といた器質的な異常によって、その症状の1つとして便秘が現れるタイプです。
疑わしい症状があった場合には、すぐに受診をしてください。
女性に便秘が多い理由
 日本人女性の半数以上が便秘持ちと言われています。女性が男性よりも便秘になりやすい理由には、以下のようなものがあります。
日本人女性の半数以上が便秘持ちと言われています。女性が男性よりも便秘になりやすい理由には、以下のようなものがあります。
筋力の差
便を先に送り出したり、排便する際には、筋肉(主に腹筋)を使います。
女性は男性よりも筋肉がつきにくいため、便が腸内に溜まりやすい・スムーズに出にくい傾向があります。
女性ホルモンの影響
女性ホルモンの1つである黄体ホルモンは、大腸での便からの水分の吸収を促進する働きがあります。これにより、男性と比べると便が硬くなりやすいのです。
特に月経前、妊娠初期は黄体ホルモンの分泌量が増えるため、便秘にお悩みの女性が増えます。
無理なダイエット
近年はその差は埋まりつつありますが、女性は男性と比べて、ダイエットを意識する人が多い傾向があります。その中で、食事を極端に減らす・まったく運動しないといったような無理なダイエットをすると、水分や食物繊維が不足したり、胃腸の働きが低下することで、便秘になるリスクが高くなります。
トイレに行くことへの
躊躇い
(排便を我慢する)
こちらも近年は性差がなくなりつつありますが、女性は男性と比べ、お手洗いに立つことに抵抗を覚えがちです。仕事中やデート中、旅行中などに排便を我慢する機会が多いと、直腸のセンサーが鈍り、便秘になってしまうことがあります(直腸性便秘)。
便秘の検査
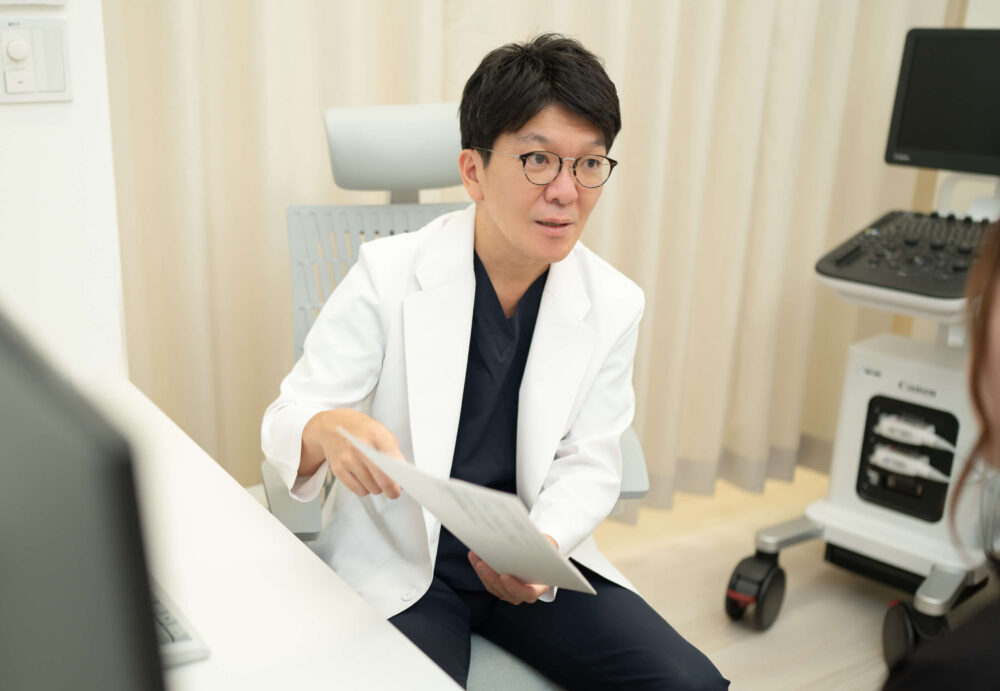 まずは問診で、便の性状、排便の頻度、その他便・排便にかかわるお悩み・症状、生活習慣、既往歴、服用中のお薬などについてお伺いします。また診察では、必要に応じて腹部の触診・聴診をします。
まずは問診で、便の性状、排便の頻度、その他便・排便にかかわるお悩み・症状、生活習慣、既往歴、服用中のお薬などについてお伺いします。また診察では、必要に応じて腹部の触診・聴診をします。
その上で、レントゲン検査、腹部超音波検査、大腸カメラ検査などを行い、診断します。当院では、内視鏡の専門医による安全性・確実性の高い、苦痛の少ない大腸カメラ検査を行っております。
どうぞ、安心してご相談ください。
当院では腸内フローラ検査が可能です
腸内では、多種多様の細菌が生息しており、そのバランスはエネルギーの産生や代謝、感染予防、肥満予防などにかかわっています。そしてこの腸内の細菌叢のことを「腸内フローラ」と呼びます。
当院では、便から腸内フローラのバランスなどを調べる腸内フローラ検査(自費)を行っています。腸内フローラに関するさまざまなデータ、疾患リスクなどが分かり、よりお一人おひとりに合った生活習慣の改善が可能になります。ご希望の方は、ぜひご利用ください。
溜まった便はどうやって出す?便秘の解消・治療方法
生活習慣の改善
 水分・食物繊維を多めに摂る、適度な運動をする、規則正しい生活をする、十分な睡眠をとるといった、基本的なことが大切になります。
水分・食物繊維を多めに摂る、適度な運動をする、規則正しい生活をする、十分な睡眠をとるといった、基本的なことが大切になります。
また、排便習慣に問題がある場合には、その改善のための指導をします。毎日決まった時間(朝食後などが理想です)にトイレに行く、その他のタイミングでも便意を感じた時にはすぐにトイレに行く、いきまない、便が出ない場合は3分ほどで切り上げるといったことが重要になります。
薬物療法
 お薬を使って便秘の解消を図る方法です。
お薬を使って便秘の解消を図る方法です。
腸の運動を促進する緩下剤、便をやわらかくする軟便剤、腸の働きを活性化する腸管刺激剤、腸内の水分量を増やすオスモチック整腸剤、腸内の善玉菌を増やすプロバイオティクスなどがあります。
便秘のタイプや体質などに応じて、お一人おひとりに合ったお薬を選択します。