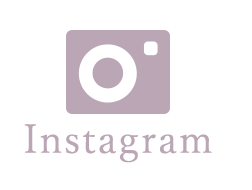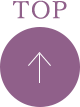以下に該当する方は要注意!

- 便潜血検査で陽性だった
- トイレットペーパーや下着に血がついていた
- 血液のようなものが便に混じっていた、付着していた
- 便の色が普段と違う
- 排便後、便器が真っ赤になっていた
- 黒い便(タール便)が出た
- 便潜血検査で去年陽性だったが、今年は陰性だったので安心している
- 血液検査で貧血を指摘された
血便、便潜血とは
 健康な人の便には、血液が含まれているということがありません。
健康な人の便には、血液が含まれているということがありません。
「血便」とは、何らかの理由により、便に血液が含まれていることを指します。べっとりと付着していたり、混ざっていたりと、血液が含まれる形や量はさまざまです。
そして血便のうち、肉眼では分からないくらいの微量な血液が混じっている状態を「便潜血」と言います。便潜血の有無は、大腸がん検診などでも行われる便潜血検査で調べることができます。
血便が出た時、便潜血検査で陽性だった時には、大腸などの消化管で出血が起こっているということですので、放置せずお早目にご相談ください。
血便の種類
血便は、以下のように分類されます。
鮮血便
鮮やかな赤色の血液が便に付着している・混じっているタイプです。また、便が出た後に、サラサラした血液だけが出るということもあります。
大腸など肛門から近い消化管から、あるいは肛門から直接(痔など)出血しているものと考えられます。
暗赤色便
黒っぽい赤色の血液が便に付着している・混じっているタイプです。一見して、血液だと分からないこともあります。
大腸の奥、または小腸などからの出血が想定されます。
粘血便
血液とゼリー状の粘液が便に付着している・混じっているタイプです。
ウイルスや細菌などへの感染、潰瘍性大腸炎、クローン病などの病気を考えます。
タール便
タールのような、黒い便のことを指します。
血液が時間をかけて酸化したためにこのような色になります。食道や胃、十二指腸からの出血を疑います。
便潜血
冒頭でご説明した、肉眼では確認できないくらいの微量の血液が混じっている状態です。便潜血検査で陽性だった場合に、便潜血と判定されます。
血便の原因
血便が起こった場合には、大腸などの消化管から、あるいは肛門から出血しているという意味になります。
大腸がん、潰瘍性大腸炎・クローン病、虚血性大腸炎、痔など、さまざまな疾患が原因となります。また食道や胃・十二指腸の病気が原因になることもあります。
便潜血検査で一回だけ陽性が出る原因
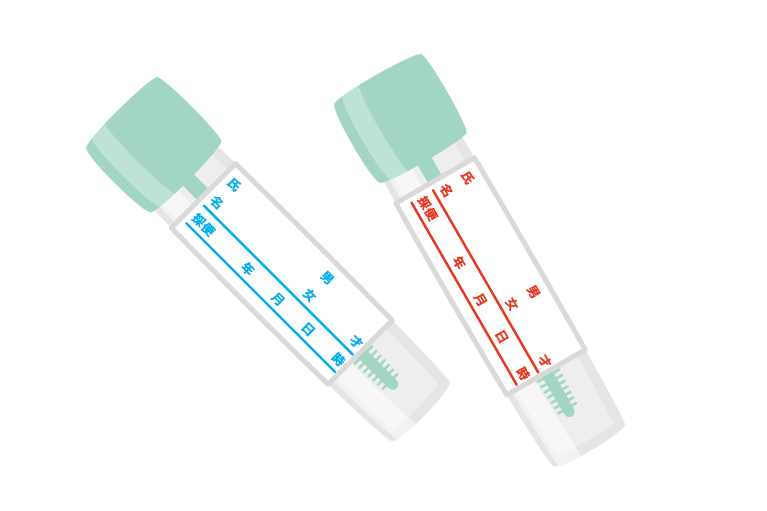 大腸などに病気があるからといって、必ずしも常に出血しているとは限りません。
大腸などに病気があるからといって、必ずしも常に出血しているとは限りません。
そのため、去年の便潜血検査で陽性だったけれど、特に治療をしていないのに、今年は陰性になるというケースが見られます。大腸がんなどの進行性の病気、自然治癒が期待できない病気であっても、こういったことが起こります。
つまり「今回は陽性だったけれど、次回で陰性になれば大丈夫」ということにはならないのです。一度でも陽性の判定が出た方は、他に症状がなくても必ず精密検査として、大腸カメラ検査を受けるようにしてください。
大腸がんの確率について
 便潜血検査を受けた人のうち、陽性となるのは約5~7%です。また陽性の人のうち、約20%で大腸ポリープが、約2~3%で大腸がんが見つかります。
便潜血検査を受けた人のうち、陽性となるのは約5~7%です。また陽性の人のうち、約20%で大腸ポリープが、約2~3%で大腸がんが見つかります。
だた、陽性になった人も3割以上が精密検査として大腸カメラ検査を受けていないという現状があります。見つけられた・治せたはずの大腸がんを見落とさない・手遅れにさせないためにも、便潜血検査を積極的に受けること、陽性だった場合には大腸カメラ検査を受けることが大切です。
血便、便潜血を引き起こす疾患
大腸がん
血便を伴う病気として、もっとも危険度が高い病気です。原因としては、欧米化した食生活、肥満、運動不足、喫煙、お酒の飲み過ぎ、遺伝的要因などが挙げられます。血便以外の症状には下痢・便秘、便が細くなる、腹痛、体重減少などがありますが、いずれもある程度進行してから出現します。
大腸ポリープ
大腸ポリープが大きくなると、出血をしたり、がん化したりといった可能性が高くなります。実際にほとんどの大腸がんは、大腸粘膜に直接できるのではなく、大腸ポリープががん化して発生します。大腸がん以上に症状の少ない病変ですが、大きくなると血便、便秘、腹痛などが見られることがあります。
潰瘍性大腸炎・クローン病
どちらも炎症性腸疾患に分類されます。血便の他、下痢や腹痛、体重減少などの症状が見られます。免疫の異常によって、消化管で炎症が起こります。厚生労働省より難病指定を受けていますが、適切な治療によって症状をコントロールすることが可能です。
大腸憩室炎
慢性便秘などによる腹圧の上昇によって、大腸の粘膜が小さな部屋のように外側へと飛び出してしまい(大腸憩室症)、そこで炎症が起こる病気です。血便の他、腹痛や吐き気、発熱などの症状が見られます。時に大量の出血を伴い、入院が必要になることもあります。
虚血性大腸炎
大腸粘膜へと血液を送る血管が障害され、大腸が虚血状態になる病気です。便秘、生活習慣病や加齢に伴う動脈硬化、ストレス、脱水状態、冷えなど、さまざまな原因があります。左側腹部~下腹部にかけての強い痛み、下痢、血便を三大症状とします。
感染性腸炎(細菌性)
ウイルスや細菌などの病原体への感染を原因として起こる「感染性腸炎」では、腹痛、下痢、発熱、吐き気、嘔吐などの症状が見られます。そのうち細菌性の場合には、血便を伴うことがあります。
胃・十二指腸潰瘍
ピロリ菌感染、鎮痛剤の副作用などを原因として、胃や十二指腸の粘膜が深くえぐれてしまう病気です。胃痛、背中の痛み、胸やけ、吐き気、貧血などの症状を伴います。重症例では、吐血や血便(タール便)を伴います。
胃がん
ピロリ菌の感染、塩分の過剰摂取、喫煙などが原因となるがんです。ある程度進行してから、胃痛、胸やけ、吐き気、食欲不振などの症状が現れます。がんから出血すると、吐血や血便(タール便)に至ります。
食道がん
喫煙・飲酒を二大原因として発症するがんです。飲み込みづらさ、胸や背中の痛み、声がれ、咳、吐き気、貧血、体重減少、血便(タール便)などが症状として挙げられますが、初期はほぼ無症状です。
いぼ痔・切れ痔
いぼや切れ痔でも、血便が出ることがあります。いぼ痔の場合は外痔核または脱出するようになった内痔核で出血が見られます。当院は肛門科でのいぼ痔・切れ痔の治療にも対応しておりますので、安心してご相談ください。
血便、便潜血が出た場合の検査
問診
症状(特に便の色や状態、排便習慣)、既往歴、服用中のお薬、生活習慣などについて詳しくお伺いします。また必要に応じて、腹部の触診や聴診を行います。
血液検査
貧血、炎症、感染の有無などを調べることができます。
直腸診
肛門または直腸から出血を起こしている可能性が高い場合のみ、実施します。医師が手袋をし、麻酔ゼリーを使用して肛門・直腸の状態を調べます。
腹部エコー
腸管の炎症、虚血の有無などを調べることができます。痛みなどの不快感、被ばくのない、患者様のご負担の少ない検査です。
大腸カメラ(大腸内視鏡)検査
血便の状態や他の症状から大腸の病気が疑われる場合には、肛門から内視鏡を挿入する大腸カメラ検査を行います。大腸全体の粘膜を仔細に観察し、出血の原因となる炎症や潰瘍、がんなどの有無を調べます。疑わしい病変を発見した場合には、組織を採取する生検も行います。
胃カメラ(胃内視鏡)検査
タール便などがあり、上部消化管の疾患が疑われる場合には、口または鼻から挿入する胃カメラ検査を行います。食道、胃、十二指腸の粘膜を仔細に観察し、出血元の炎症や潰瘍、がんなどの有無を調べます。